
|
(5)薄明時および夜間は夜間用双眼鏡を、しかも倍率の大きいものを使用すべきである
(6)眼鏡をかけたまま双眼鏡を使用するときは、アイ・ポイントより後方で見ることになり視野が狭められることを知らねばならない。
(7)双眼鏡の使用に当たっては、自分の眼によく調整し、一度調整したものはそれを崩さないよう注意しなければならない。したがって、他の人との共用は極力避けるべきである。
(8)取り扱い上の注意点としては、衝撃を与えない、長時間直射日光にさらさない、湿気の多い保管場所は避ける、使用後のレンズの手入れ等である。
4. もう一つの見張り
われわれが外界から得る情報の80%以上が視覚によるものであるといわれているところから「見張り」といえば視覚によるものと思い込むのもやむを得ない。
ところが、海上衝突予防法第5条「見張り」の項では「すべての船舶は、その置かれている状況及び衝突のおそれを十分に判断できるように、視覚及び聴覚により、また、その時の状況に適したすべての利用可能な手段により、常に適切な見張りを行っていなければならない」と定めている。すなわち、場面に応じて視覚、聴覚その他あらゆる感覚器官を駆使して適切な「見張り」を励行することを規定している。
そこで、海上衝突予防法にいう他の適切な見張りもあることを、一例をあげて参考に供しよう。
図4は昭和61年(1986年)4月27日午前8時過ぎ、佐渡・両津港外に錨泊中の練習船大成丸の船橋(眼高10.6m)で、濃霧中に入港する佐渡汽船フェリーの諸情報を記録したものである。図中の船速と距離はレーダーによった。この記録からいろいろなことが読み取れるが、注目したいのは視覚情報が制限された場合の聴覚情報の重要性である。だからこそ船橋内の雑音の管制、船橋の窓の解放等が要求されるわけである。
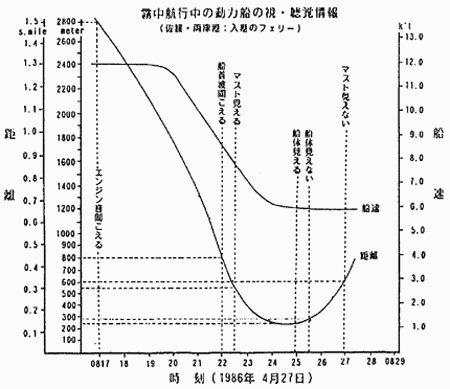
図4 霧中航行中の動力船の視・聴覚情報
前ページ 目次へ 次ページ
|

|